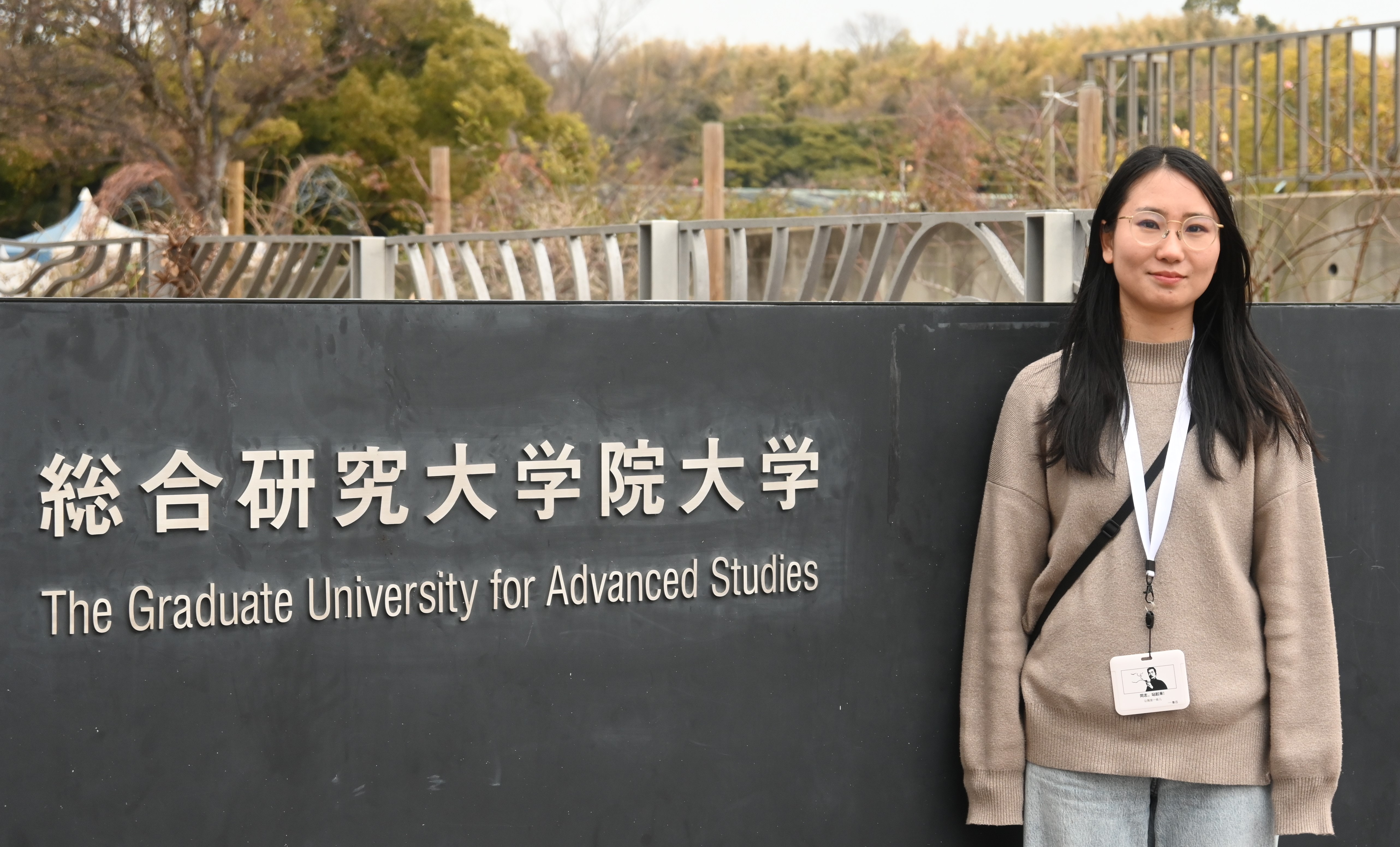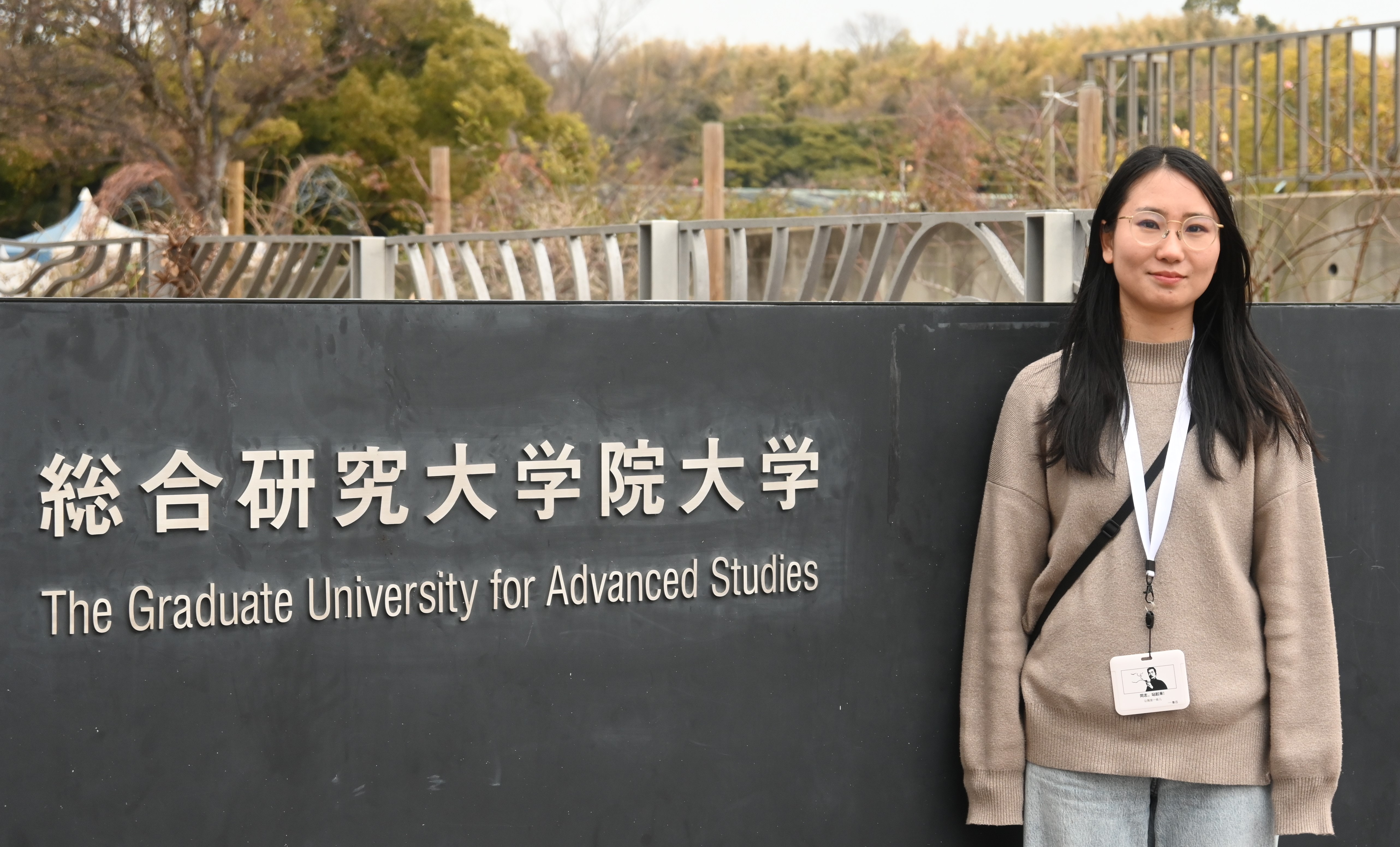 劉丹さん
劉丹さん
-
はじめに、日本に来られた経緯を教えていただけますか。
劉丹さん
: はい。私は中国の大学で日本語学科に所属しておりまして、大学3年生の時に、交換留学生として協定先の沖縄の大学に約1年間留学しました。そこでは日本語の語学の授業だけでなく、現地の学生と同じように多くの授業を選択することができ、教育学や歴史学、日本の近代文学や古典文学などを履修しました。その中で、社会人類学者の中根千枝先生の『タテ社会の人間関係』という本を読み、文化人類学に魅了されたんです。これが私の人類学との最初の出会いでした。それから人類学をもっと勉強したいと思うようになり、中国の大学を卒業後、研究生として再び沖縄に渡り、大学院への進学を目指しました。
 藤木信穂さん
藤木信穂さん
-
学部時代に日本語を学ぶなど、もともと日本に興味があったのですね。
劉丹さん
: そうですね。日本と中国は近いですし、さまざまな関わりを持ってきたと思うんです。特に、周囲に日本のアニメや文化が好きな友達がたくさんいて、なぜ日本がこんなに魅力的な国になったのかが知りたくて日本語を専攻しました。
- 人類学を志して入学した沖縄の大学院では、どのような研究をされたのですか。
劉丹さん : 修士課程のテーマ決めはかなり悩んだのですが、自分の身近な問題を取り上げようと思い、中国の出稼ぎ労働者の貧困問題について研究しました。特に、親が出稼ぎに行っている間、留守番をしている農村部の「留守児童」の教育問題を扱いました。彼らの多くは農村に残され、親には年に1回ほどしか会えません。私の出身地にはこうした留守児童がたくさんおり、私自身もまた留守児童でした。留守児童は低学力に苦しんだり、対人関係に悩んだりといったさまざまな問題を抱えているケースが多いのです。そのため、成人しても十分な収入が得られず、結果的に、自分の親と同じように出稼ぎに行かざるを得ないという悪循環に陥っています。この問題を解決するにはどうしたら良いのかと考え、研究テーマにしてきました。
 指導教員の奈良雅史准教授(左)と劉丹さん(右)
指導教員の奈良雅史准教授(左)と劉丹さん(右)
-
修士課程を経て、総合研究大学院大学の博士課程へ進まれました。総研大を選んだ理由を教えてください。
劉丹さん
: 修士課程の時にご指導いただいた人類学の先生から、総研大の地域文化学専攻を勧めてもらったのがきっかけです。その後、現在の指導教員である奈良雅史先生の論文を読んで感銘を受け、総研大の入試説明会で先生に直接お目にかかり、個別面談で話をさせてもらったことで、先生の指導を受けたいと強く思いました。私も自分には人類学の知識が足りないと感じており、人類学の教員が多くいる国立民族学博物館(みんぱく)は最適だと思いました。図書室の蔵書が豊富なことも大きな魅力でしたね。実際に入学し、フィールドワークに関する手厚いサポートや、他大学との活発な共同研究、国際シンポジウムの開催など、大変恵まれた環境に満足しています。
-
日本語がとてもお上手ですが、どのように勉強してこられたのですか。
劉丹さん
: ありがとうございます。私自身は、うまく表現できないこともまだまだ多いですが。ただ、今よりもっと以前、交換留学時や修士課程の頃は、言葉でかなり苦労し、涙することも多かったです。ですが、たくさんの授業を履修し、ゼミの先生と本を読み進める中で、先生や仲間の指導を受けながら、少しずつ上達してこられたのかなと思います。授業のおかげで日本文学にも親しむことができました。一方、ゼミ生に中国語に興味のある方がおり、土日には私が講師を務め、中国語の勉強会を開くこともありました。言葉は使えば使うほど慣れていくものだと感じますし、周りの人々からの指摘もありがたく思います。
総研大に入ってからは、自分の発表をわかりやすく伝える練習をする機会にも恵まれました。2022年には、総研大の社会連携事業「未知への挑戦:若手が語る最先端研究」に参加し、高校生に向けて自身の研究を紹介しました。その際、2日間にわたる発表のリハーサルを行い、先生や他の参加者である他専攻の院生からプレゼンテーションに関する助言をもらうことができました。自身の語学習得の道を振り返ってみると、このような積み重ねが大事だと思います。また、学会発表や論文執筆では日本語を使うことが多いですが、最近は国際学会で発表する機会もあり、英語の勉強にも力を入れているところです。
-
現在の研究についてうかがいます。なぜハス農家を対象とされたのでしょうか。
劉丹さん
: 実は、ハス農家を対象にした背景には予想外の展開がありました。当時、私は穀物の安定生産や農業の集約化、農民の収入増などを目指し、中国政府が2000年以降、活発に進めた農地制度の改革による村社会の変容に関心を持っていました。これに関してオンライン調査を進める中で、ハス農家に偶然出会い、協力してもらえることになったんです。ハスの栽培というと、日本ではレンコンをイメージするかもしれませんが、私の調査地では、ハスの実の収穫を目的としています。ハスの実は中国では古くから、皇帝や貴族への貢ぎ物として扱われ、さらに栄養分が高いことから、現在では漢方薬や高級食材として用いられています。家庭料理でもおかゆやスープに入れたり、中秋節に食べる「月餅」に使われたりするなど、ハスの実はとても身近な食材であり、幅広い場面で利用されています。また、ハス農家には出稼ぎ出身者が多く、修士課程のテーマともつながっています。
-
人類学的な研究の特徴とも言える、フィールドワークはどのように進めるのですか。
劉丹さん
: フィールドワーク先は農業開発が活発な地域です。現在、私は1年を一つのサイクルとし、半年から10カ月程度をかけてフィールド調査に出て、残りの数カ月間でデータを整理するといった要領で進めています。現地では、朝6時くらいから、夜は7-8時くらいまで、農家の人たちのコミュニティに入り、ハスの栽培に関わる除草作業を一緒にしたり、肥料の散布をしたり、ハスの実の加工場で加工のプロセスに参加させてもらったりというように、彼らと常に活動を共にしています。ハスは夏に花が咲くので、夏場の作業などは暑くて大変なことも多いですね。栽培と加工作業を通して、現地でのネットワークもどんどん広がり、研究対象とする人物は総勢100人くらいになるでしょうか。
劉丹さん
: 私の場合、インタビューを行う期間は意外と短く、ハスの実の収穫が終わった10月以降に集中的に実施させてもらうことが多いです。ですので、普段、作業活動を行う中での雑談などから、自然に出てくる情報を大事にしています。コミュニティの中に入り込むに当たっては、うまくいかないことも多々ありますが、調査地にできるだけ足を運び、長く滞在し、自分自身が現地の人の視点を持てるよう努めることが重要だと思っています。文献調査などによって自分があるテーマに関心を持っていても、現地の人とは見方が異なることが往々にしてあります。そのような場合は、相手に質問を投げかけても、適当にあしらわれてしまうなど、うまくいきませんね。時間をかけて信頼関係を築くことが大切です。
-
なるほど。みんぱくで送る学生生活の楽しみをお聞かせください。
劉丹さん
: みんぱくは博物館を持つ研究機関であり、普通の大学とは異なる素晴らしい環境だと思います。学生が少人数なので、さまざまな分野の教員にきめ細かく指導してもらえます。研究に行き詰まった時は、博物館の展示を見たり、万博公園を散歩したりして気分転換をしています。緑豊かなこのような環境で研究ができることは本当に贅沢ですね。毎年、年末に院生が主催しているエスニックパーティーなども楽しいです。タイやモンゴル、カナダ、フランスなど、各学生が自分の研究対象とするフィールドの国の料理を作って、先生たちと一緒に食べながら盛り上がるんです。
劉丹さん
: 2回のフィールドワークを終え、現在はデータを分析しているところなのですが、皇室への貢ぎ物から、国民的な嗜好品として発展してきたハスに関する民族誌を書くことを目指しています。私は人類学に接してから、自分の当たり前を疑うようになりました。例えば、日本の社会や、部族社会など、それぞれの民族誌を読み解くことで、自分のいる世界がより立体的に見えるようになったと感じています。日本に来る前は、中国の農村部の実態に注意深く目を向けることはなかったのですが、やはり、自国を離れることで見えてくるものがありますね。今後も研究を続け、将来は研究の道に進みたいと思っています。
-
最後に、劉さんのように日本に留学したいと考えている学生さんや、研究者に興味を持つ学生さんへメッセージをお願いします。
劉丹さん
: 中国では、日本の大学や研究室に関する情報がSNSなどで拡散されており、そうした情報ももちろん参考になるのですが、留学を考えている方には、あまり先入観を持たずに考えてもらいたいですね。研究テーマを設定する上では、これまで多くの方が研究を積み重ね、成果を挙げてこられた中で、もう研究の余地がないのではないか、といった悩みがたびたび聞かれます。ですが、自分の問いや感性を大切にしながら、先行研究をしっかり勉強することで、自分の研究が位置づけられてテーマが見つかることもよくあります。“巨人の肩の上に立つ”という姿勢で、研究者を目指していただければと思います。
インタビュアー/記事執筆
シンメトリ株式会社 代表取締役/科学技術ライター
藤木信穂
動画内用語解説
農民工:
1958年に制定された「中国戸籍登記条例」により、中国の戸籍は農業戸籍と非農業戸籍の2つに分けられた。これらは、それぞれ農村戸籍、都市戸籍とも呼ばれている。戸籍制度は公共サービスや年金制度と密接に関連しており、長年にわたり農村戸籍から都市戸籍への変更は厳しく制限されていた。
1990年代に入ると、中国の広東や浙江などの沿岸都市部では労働集約型産業が集積し、農村部から沿岸都市部への出稼ぎ労働者が急増した。農村戸籍を持ちながら工場や工事現場で働く彼らは「農民工」と呼ばれるようになり、その数は数億人を超え、世界の工場と呼ばれる中国経済を支える重要な役割を果たしている。
しかし、多くの場合、農民工は社会的な弱者と見なされ、生活環境や労働条件にはさまざまな課題がある。低賃金や過酷な労働環境、社会保障の不十分さ、さらには子どもの教育問題などが問題として指摘され、これらの課題についての研究が行われている。
合作社:
ここで言う「合作社」とは「農民専業合作社」を指す。これは農民が主体となり、自主的に組織・運営する互助型の経済組織である。具体的な形態としては、零細農家が土地を集めて大規模な栽培事業を行うものや、農業用機械を活用して農作業の委託業務を提供するものなどがある。
2006年10月31日、中国人民代表大会常務委員会により「中華人民共和国農民専業合作社法」が制定され、農民専業合作社は正式に法人格を持つ経済主体として認められた。この法案に基づき、政府は農業の産業化を進めるため、農民専業合作社の設立を奨励し、農業機械の購入補助などの優遇政策を実施した。
「合作社」という言葉は中国社会を理解するうえで重要なキーワードの一つであり、その歴史は1920年代にまで遡る。農民専業合作社以外にも、以下のような異なる種類の合作社が存在する。
- 供销(gongxiao)合作社(農産物の流通や生活物資の供給を行う協同組織)
- 信用合作社(農民を対象とした金融協同組合)
合作社の歴史や現状に関心のある方は、以下の書籍もご参照ください。
- 河原昌一郎 2009 『中国農村合作社制度の分析』農山漁村文化協会
- 山田七絵 2020 『現代中国の農村発展と資源管理』東京大学出版会