時代の風
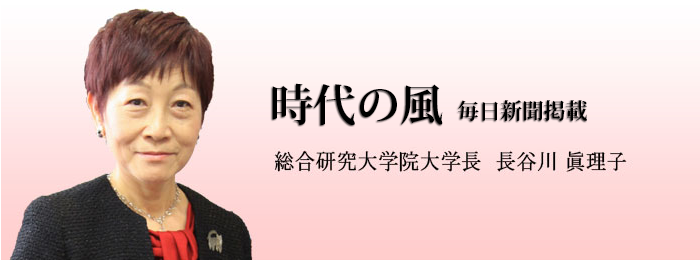
私は、2016年4月から、毎日新聞に『時代の風』というコラムを、6週間に1回、連載しています。 現代のさまざまな問題を、進化という別の視点から考えていきますので、ご興味のある方はご一読ください。
ロボットの未来 AIは「人生」語れるか
中学・高校のころ、SF小説が大好きで、早川書房のSFマガジンを愛読していた。いつだったか、星新一氏による、未来の地球を描いた短編があった。
地球全体におびただしい数の道路網が張り巡らされていて、そこをタイヤが走り回っている。道路に穴が開くなどすると、自動的に修復される。タイヤのパンクも、同じく自動修復。こうしてタイヤは道路を無限に走り続けるのだが、人類はもう絶滅してしまっていて、地球には誰もいない。
子どもの私には、この話のどこがよいのかよくわからなかったが、今でも鮮明に覚えているということは、よほど印象深かったのだろう。道路とタイヤというのは、まさにモータリゼーションが始まるころの日本を象徴しているが、「自動修復」というアイデアや、意味なしに走り続けるという設定に、現代の人工知能(AI)とロボットを感じさせるではないか。
***
最近、英国の科学雑誌で、人間のようなロボットが出てくる映画の紹介記事を読んだ。両親を亡くした9歳の子どもの世話をし、その子を、肉体的および精神的な危害から守るように、という使命を受けたヒューマノイド・ロボットである。しかし、ロボットには、「子どもを守り育てる」というのがどういう意味なのかはわからない。だからロボットはすべての「危害」を除去し、子どもをすべての悪いことから遠ざける。
その結果、子どもは何も学ばないし、成長しない。評者は、子どもを育てることの本質は、危険から守ってあげながらも、さまざまな事態に際し、自分でなんとか対処できるようにさせることだと言う。この意味がロボットにわかるか?
それを言えば、「意味」とはどういう意味だろう? とても難しい問題なのだが、意味とは、単語や文章の理解だけの話ではない。その言葉が発せられた状況、過去の記憶、本人や他者の感情、などなどのすべてを踏まえて、その場のそのことだけにとどまらずに、総合的にとらえられる実感なのではないか。
そのことには、自分にからだがあり、からだで動いて経験し、成長し、やがて死んでいくことを知っている、という前提があるのではないか。だから、生身のからだを持たず、成長し、学習し、膨大な記憶のもとで人生観を築いてきたのではないロボットには、「意味」がわからないのだと思うのである。
現在のチャットボットなどは、他の人間たちが吹き込んださまざまな言語データをもとに、ある単語と別の単語との結び付きを学習することによって、一見まともな会話をする。しかし、それらが発している言葉の意味はまったくわかっていない。では、やがて彼らも意味がわかるようになるのだろうか?
ロボットやAIの研究者たちは、なんとか意味がわかるロボットを作ろうとしているし、賢いプログラムさえできれば、可能だと考えているようだ。しかし、どこまで行っても、からだがなく、それが成長しつつ経験を記憶し、やがて死ぬのが運命だとどこかで知りながら生きている、という存在でなければ、「意味」を理解することに意味はないと思うのである。
***
そして、そもそも「意味」のわかるロボットを作ることにどんな意味があるのだろうか? それは人間を作ることだろう。さらに、人間では、同じ言葉や事態を前にしても、人によってその意味は異なる。ロボットはどんな意味を採用するのだろう? それはロボットごとに異なるのだろうか?
私の大好きな小説の一つに、サマセット・モームの「人間の絆」がある。その主人公は、若いころからずっと人生の意味を探して悩む。師とあおぐ人が言うには、「人生の意味はペルシャ絨毯(じゅうたん)にかいてある」。そこで、もらったペルシャ絨毯の切れ端を壁にかけて、毎日 眺めるのだが、よくわからない。ある日、気付く。人生に意味はないのだと。人生とは、ペルシャ絨毯の職人が気の向くままに織り込んでできた模様のようなもので、一生懸命生きてきた結果に過ぎないのだ。
私たちは、限りある人生を生きている存在だからこそ、さまざまな事柄にそのつど意味を見いだし、それらをつなげて毎日を暮らしている。それがわかる機械ができたら、それは、ある種の他人と同様にやっかいな存在に違いない。=毎週日曜日に掲載
(2023年3月26日 )
